人気YouTuberの「オワコン」化:4つのケーススタディと考察
- 2025-01-29
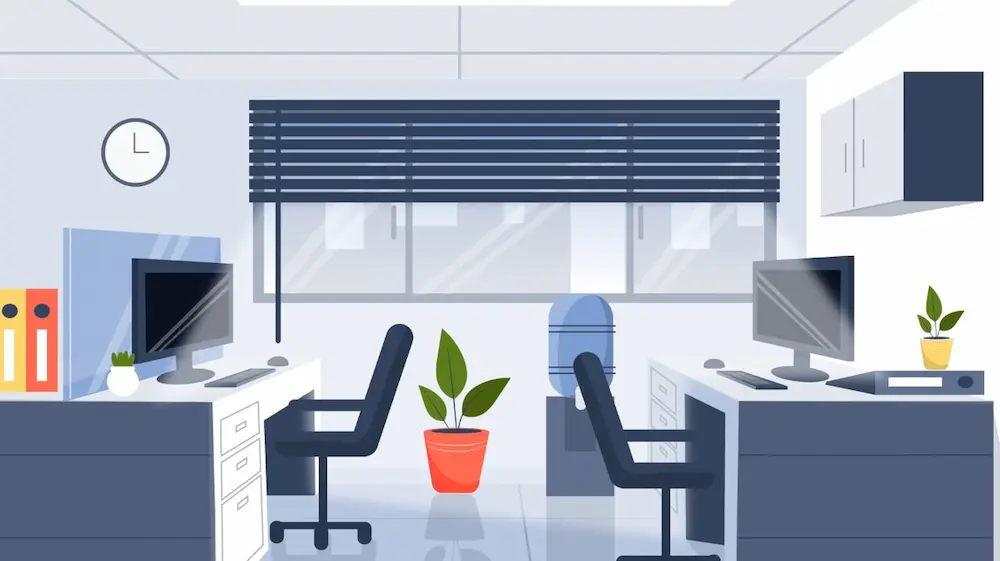
人気YouTuberの「オワコン」化:4つのケーススタディと考察
近年、YouTubeは個人の表現の場として、またビジネスの場として大きな発展を遂げています。しかし、人気絶頂期を誇ったYouTuberが、様々な理由から「オワコン(終わったコンテンツ)」と揶揄される現象も散見されます。本記事では、そんな「オワコン」化の危機に直面した、あるいは直面したとされるYouTuber4組のケーススタディを通して、その原因と背景を深く掘り下げて考察します。
ケーススタディ1:銀ダンボーイズ→オワコンボーイズの崩壊
概要: 2015年に活動を開始した人気YouTuberグループ「銀ダンボーイズ」。渋谷スクランブル交差点や大阪の道頓堀などでの企画動画や過激なドッキリなどで人気を博し、チャンネル登録者数は100万人を突破しました。しかし、2017年の仮想通貨を用いたサービス「バイナンス」に関する騒動に関与したことをきっかけに活動休止。その後、リーダーのいっくんさんの卒業発表(2021年9月)、新リーダーとして元お笑い芸人のたつんさんを迎え入れ「オワコンボーイズ」に改名するも、登録者数200万人に到達しなければ解散という目標を達成できず、2022年8月7日に解散しました。そして2023年2月、メンバーのモーリーさんが売春斡旋の疑いで逮捕されるという衝撃的な事件が勃発しました。
問題点:
- 仮想通貨関連の騒動: 2017年の仮想通貨騒動への関与は、グループのイメージを大きく損ないました。信頼性の低下は、視聴者離れを招く大きな要因となりました。
- リーダーの卒業: リーダーのいっくんさんの卒業は、グループの軸となる存在を失ったことを意味します。グループの継続に大きな影を落としたと言えるでしょう。
- 改名と解散: 「オワコンボーイズ」という改名自体が、グループの現状を自嘲的に表現したものであり、ネガティブなイメージを定着させてしまった可能性があります。目標達成できず解散したことも、視聴者の落胆を招きました。
- モーリーさんの逮捕: メンバーの逮捕という重大な事件は、グループの活動に終止符を打つだけでなく、関係者にも大きな影響を与えました。
考察: 銀ダンボーイズのケースは、初期の成功体験に胡座をかき、リスク管理を怠った結果、急速な衰退と崩壊を招いた典型例と言えます。仮想通貨関連の騒動への対応の遅れや、リーダー不在の後のグループ運営の不備、そしてメンバーの不祥事と、様々な要因が重なって「オワコン」というレッテルを貼られる結果となったと言えるでしょう。
ケーススタディ2:ジョーじさんの「オワコン」化論争
概要: 日本のYouTuber、ジョーじさんは、自身を「メンタルコーチ」と称し、YouTubeで「男磨き」を啓発する動画を制作・配信しています。青山学院大学中退という高学歴も持ち合わせていますが、独特な語り口調と発言から「オワコン」と揶揄される声も上がっています。特に「危機感日記」と銘打った動画において、「スポーツ経験のない男」「運動経験が少ない男」「部活動に入った経験のない男」に対して強い危機感を訴えたことが、一部視聴者から批判を招きました。
問題点:
- 「危機感日記」動画の炎上: 「危機感日記」動画における発言は、一部の視聴者からインキャやチー牛といったカテゴリーに分類される人々を軽視していると捉えられ、炎上しました。発言内容の選び方や表現方法に問題があったと言えるでしょう。
- 一部視聴者からのアンチ増加: 炎上によってアンチが増加し、YouTubeチャンネルの更新頻度が低下。結果として、チャンネルの活動が停滞しているという印象を与えてしまった可能性があります。
- 「メンタルコーチ」という肩書き: 自身の肩書きと動画内容にギャップを感じた視聴者も少なくないでしょう。「メンタルコーチ」としての資質や実績が不十分であるという印象を与えた可能性があります。
考察: ジョーじさんのケースは、「オワコン」というレッテルの貼られ方が、必ずしもチャンネルの活動状況を正確に反映していないことを示しています。動画再生回数は依然として多いにもかかわらず、「オワコン」と揶揄されるのは、彼の発言やキャラクターに対する視聴者の認識の変化が原因と言えるでしょう。かつての強烈なキャラクターが薄れたこと、期待していた視聴者層が離れていったことが、「オワコン化」と捉えられている要因と考えられます。
ケーススタディ3:かっつーさんのVTuber関連活動への批判
概要: UUUM所属YouTuberのかっつーさんは、たこ焼き動画で知られていますが、2024年6月、人気VTuberの白銀ノエルさんの夏色まつりでのX(旧Twitter)でのフォロー報告をきっかけに、VTuber関連の投稿や配信を開始しました。しかし、このVTuber界隈への「すり寄り」が、一部視聴者から批判を招きました。さらに、加藤純一さんの不倫騒動の際、ミラー配信を行ったことも、批判を招く要因となりました。
問題点:
- VTuber界隈への「すり寄り」: それまでとは異なる分野に急に参入したことで、既存の視聴者層とのずれが生じました。
- 加藤純一さんへのミラー配信: 加藤純一さんとの個人的な関係性を抜きにして、炎上商法や視聴者の感情を煽るような行為であると捉えられた可能性があります。
- 「反省」の姿勢への疑問: 反省の弁を述べつつも、自身のプライドを優先する発言は、視聴者の不信感を招いたと考えられます。
考察: かっつーさんのケースは、視聴者層の期待値とYouTuberの活動方向のミスマッチが、「オワコン化」につながることを示しています。人気に便乗したような行動や、視聴者の感情を軽視した行動は、大きな反発を招くことを改めて認識させる事例となりました。
ケーススタディ4:レペゼン地球のメンバー脱退とグループ崩壊
概要: レペゼンフォックスは、YouTubeを中心にSNSや各地のクラブ、ライブハウスで活躍する日本のDJグループです。2015年から活動を開始し、日本一を目指してドームライブを目標に掲げていましたが、2023年12月にDJ社長が失踪し、その後、メンバーが次々と脱退。結果的にグループは事実上崩壊しました。
問題点:
- DJ社長の失踪: グループのリーダーであるDJ社長の失踪は、グループの活動を完全に停滞させました。リーダー不在はグループの運営継続に大きな問題を引き起こします。
- メンバーの相次ぐ脱退: DJ社長の失踪をきっかけに、他のメンバーもグループを脱退。グループとしての活動継続が不可能になる事態に陥りました。
- 内部対立の可能性: LINEでのやり取りで、メンバー間で様々な衝突があったと推測されます。内部対立はグループ崩壊の大きな要因となります。
考察: レペゼンフォックスのケースは、リーダーの不在とメンバー間の不和がグループの終焉につながることを示しています。長期的な成功のためには、メンバー間の良好な関係性と、リーダーシップの明確化が不可欠であることを示唆しています。
まとめ:YouTuberの「オワコン」化を防ぐために
上記の4つのケーススタディを通して、「オワコン」化には様々な要因が複雑に絡み合っていることがわかります。共通して言えることは、以下の点です。
- 視聴者との信頼関係の構築: 視聴者との信頼関係を築き、維持することが、長期的な成功には不可欠です。
- リスク管理の徹底: 不祥事やトラブルへの備えとして、リスク管理を徹底する必要があります。
- 変化への対応力: 常に変化する視聴者のニーズや市場の動向に対応していく柔軟性が必要です。
- メンバー間の連携: グループ活動においては、メンバー間の良好な関係性を維持することが重要です。
- 明確なビジョンと計画: グループとして、あるいは個人として、明確なビジョンと計画を持ち、それに基づいて活動を進めることが大切です。
これらの点を踏まえ、YouTuberは常に自己研鑽を行い、視聴者とのコミュニケーションを大切にしながら、変化に対応していく必要があります。「オワコン」というレッテルを貼られないためには、継続的な努力と、視聴者との信頼関係が不可欠なのです。 YouTubeという世界は、華やかな成功の裏に、多くの困難とリスクが潜んでいることを、これらのケーススタディは改めて私たちに教えてくれます。
