SNS精子提供:手軽さの裏に潜む闇と、2021年の訴訟事例から学ぶリスク
- 2025-02-15
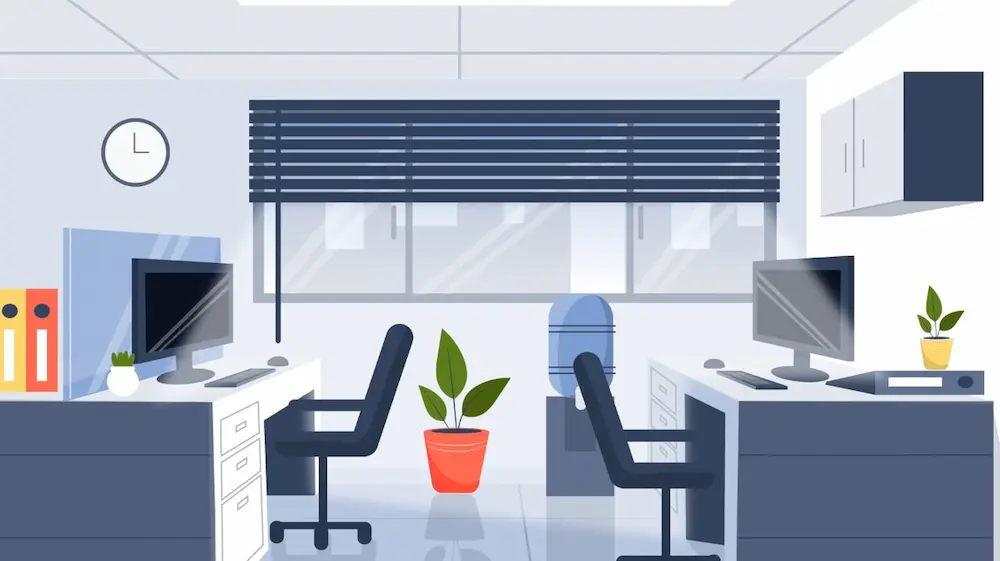
SNS精子提供の現状と、その闇
近年、SNSを通じた精子提供が急増しています。手軽さと匿名性というメリットの裏には、医療的、法的、倫理的な深刻なリスクが潜んでいます。本記事では、病院での精子提供の歴史と現状、SNS精子提供の現状、そして2021年に起こった訴訟事例を交えながら、そのリスクを詳細に解説します。
病院での精子提供:歴史と現状
日本の精子提供は、1949年に慶應義塾大学病院が不妊治療の一環として実施したのが最初です。当初は、無精子症の夫婦に限定されていましたが、その後、性同一性障害(FTM)の夫婦にも提供されるようになりました。
現在、国内で精子提供によって生まれた子供は1万人から2万人に上ると推定されています。しかし、病院での精子提供は、法的に婚姻関係にある夫婦のみに限定されているため、同性愛カップルや選択的シングルマザーは対象外となります。この限定的な提供体制が、SNS精子提供の増加の一因となっています。
病院での精子提供の現状:
- 法的制限: 婚姻関係にある夫婦のみに限定
- 提供者不足: 慶應義塾大学病院が2018年に新規患者の受け入れを停止したことが、提供者不足を象徴する出来事として挙げられる。
- 匿名性: 提供者の情報は依頼者には伝えられないのが原則。
SNS精子提供の増加と、その背景
病院での精子提供が抱える課題、特に提供者不足と匿名性に関する制限が、SNS精子提供の増加を招いていると言えるでしょう。
SNS精子提供の増加の背景:
- 病院での提供体制の制限: 同性愛カップルや選択的シングルマザーへの提供が困難
- 提供者の増加: 匿名性を求める人や、手軽に提供できる点に魅力を感じる人が増加している可能性
- 経済的理由: 海外の精子バンク利用に比べて、費用が安価である
SNS精子提供のリスク:医療的リスク
SNS精子提供は、手軽で安価な反面、医療的なリスクが非常に高いです。
医療的リスク
- 感染症リスク: 提供者の感染症が、子供に移ってしまう可能性がある。慶應義塾大学病院では、凍結精液を用い、半年後に感染症がないことを確認してから使用している。
- 遺伝子疾患リスク: 提供者が特定の遺伝子疾患を持っている場合、その遺伝子疾患が子供に遺伝する可能性がある。遺伝子疾患の確認は、SNS精子提供では困難である。
- 近親婚リスク: 同じ提供者の精子を用いて複数の子供が生まれると、近親婚のリスクが高まる。これは倫理的に問題であるだけでなく、遺伝子疾患のリスクの増加にも繋がる。
SNS精子提供のリスク:法的・倫理的なリスク
SNS精子提供は、医療的なリスクだけでなく、法的、倫理的なリスクも伴います。
法的・倫理的なリスク
女性側(依頼者)のリスク:
- 性的トラブル・性的被害: 提供者の動機や倫理観が不明なため、性的トラブルや被害に巻き込まれる可能性がある。 性行為を求められるケースもある。
- 養育への介入: 提供者が養育に介入してくる可能性がある。個人情報は、最低限の情報(名前、住所、連絡先)しか提供しない場合でも、提供者から後々情報が漏洩するリスクがある。
- 経済的支援のトラブル: 金銭的な支援を約束されたにもかかわらず、支援が受けられないケースや、逆に搾取されるケースもある。
男性側(提供者)のリスク:
- 認知請求: 生まれた子供から、認知を請求される可能性がある。民法上の親子関係が成立し、養育費の請求などを受ける可能性も。
- 養育費請求: 子供の養育費を請求される可能性がある。特に、婚姻関係がないケースでは、男性が法的な父親になる可能性が高い。
子供のリスク:
- 出自を知る権利の侵害: 出自を知る権利が侵害される可能性が高い。日本の法律では出自を知る権利に関する明確な規定がない。
- 近親婚のリスク: 前述の通り、遺伝子疾患や倫理的な問題を引き起こす可能性。
2021年の訴訟事例:SNS精子提供の危険性を浮き彫りに
2021年、SNS上で精子提供を受けた女性が、提供者に対して損害賠償請求を行う訴訟を起こしました。この訴訟は、SNS精子提供の危険性を改めて浮き彫りにする事例となっています。
訴訟事例の概要:
- 依頼者: 35歳女性(Aさん)
- 提供者: 20代男性(Bさん)
- 経緯: Aさんは、夫との間に子供を授かれず、第2子希望。夫と同様の容姿、身長、血液型、そして東大卒という条件を満たすBさんとSNSで知り合い、精子提供を受ける。BさんはTwitter上で「精子提供@東京」と名乗り、条件を提示していた。
- 発覚: Bさんの国籍、学歴、既婚者である事が判明。
- 結果: AさんはBさんに対し、約3億3200万円の損害賠償を請求。裁判は現在も継続中。
- 問題点: Bさんの虚偽の自己紹介、契約違反、養育費問題、子供の福祉への影響など。
この事例は、SNS精子提供における情報開示の不透明さ、契約の脆弱性、そして法的・倫理的な問題を露呈するものです。
まとめ:SNS精子提供の慎重な検討を
SNS精子提供は、手軽さと匿名性を求める人にとって魅力的な選択肢に見えるかもしれませんが、医療的、法的、倫理的なリスクが非常に高いことを理解する必要があります。
特に、提供者側の情報開示の不透明さ、契約の脆弱性、そして生まれた子供が出自を知る権利が侵害される可能性、近親婚のリスクは、深刻な問題です。
SNS精子提供を検討する女性、そして提供しようと考えている男性は、以下の点をよく考えてから判断する必要があります。
- 医療的なリスク: 感染症、遺伝子疾患、近親婚のリスクを十分に理解しているか。
- 法的リスク: 認知請求、養育費請求などの法的責任を負う可能性があることを理解しているか。
- 倫理的なリスク: 子供の福祉、出自を知る権利などを十分に考慮しているか。
子供は、親の選択によって生まれるものではなく、なんの罪もない命です。親として、責任ある行動をとる必要があります。 Aさん、Bさん双方の行動には批判的な意見も少なくありませんが、何よりも、生まれた子供をどう守るか、ということが重要であると、私たちは考えます。
