「自分で考えろ」指導の功罪と、その効果的な活用法:社会人経験者による考察
- 2025-01-18
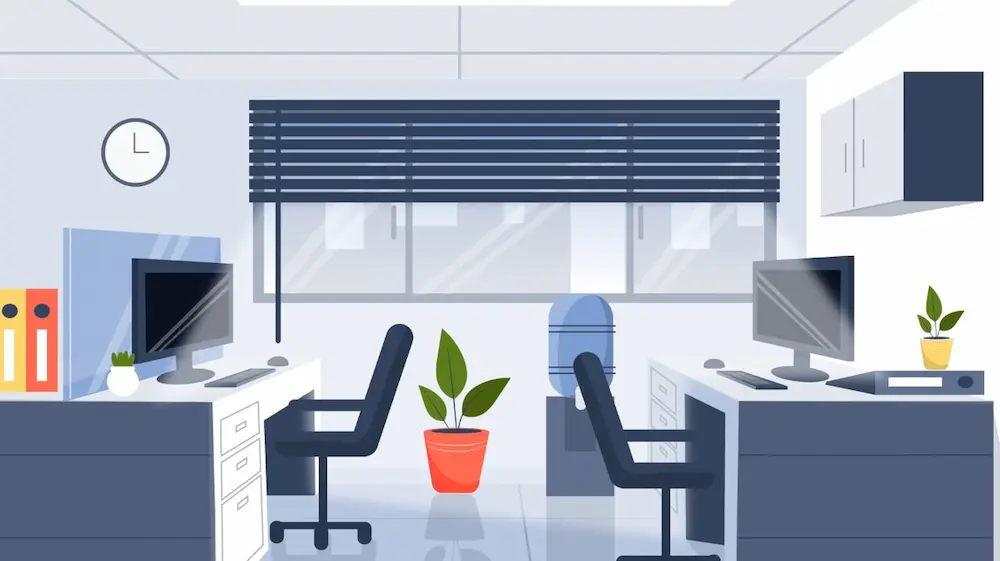
「自分で考えろ」指導の功罪と、その効果的な活用法:社会人経験者による考察
はじめに
皆さん、こんにちは!今日は「自分で考えろ」という指導について、自身の社会人経験を踏まえて深く掘り下げていきます。7年半の証券会社勤務で培ってきた経験から、この指導の有効性と限界、そしてより効果的な活用方法について考察しました。 特に、正しい「自分で考えろ」指導の在り方とは何かを、具体的な事例を交えながら解説していきます。
「自分で考えろ」指導の現実
「自分で考えろ」という言葉を、職場や家庭で一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか? 特に、子供や部下に対して、あるいは上司から言われた経験を持つ方も多いはずです。
しかし、この指導は、受け取る側にとっては時に非常に辛いものです。特に、経験不足の若手社員や、初めてのことへの対応に苦慮している人にとっては、単なる「投げやり」と受け取られがちです。
「いやいや、ちゃんと先輩が教えてくださいよ!」 「そもそも自分で考えろって、そんな指導でもなんでもないやろ!」
このような不満を抱く人は少なくないでしょう。 なぜこのような感情が生まれるのでしょうか?それは、状況によって「自分で考えろ」という指導が適切でない場合があるからです。 それはまさに、問題の性質に依存しています。
正解が定まっているものと、正解が定まっていないもの
物事を大きく2種類に分類することで、「自分で考えろ」指導の有効性を理解しやすくなります。
1. 正解が定まっているもの:
これは、パソコン操作や計算など、明確な手順や答えが存在するものです。 例えば、
「このボタンを押せば印刷できますか?」
という質問に対しては、
「エンターキーを押せば印刷できますよ」
と明確に答えることができます。 この場合、「自分で考えろ」という指導は非効率であり、適切ではありません。 指導する側も、迅速に正確な情報を提供するべきです。
2. 正解が定まっていないもの:
これは、営業や人付き合いなど、状況や相手によって最適な方法が異なるものです。 例えば、
「初対面の人に、どんな挨拶をすれば好印象を与えられますか?」
という質問には、明確な正解がありません。 長年の営業経験を持つ私は、この点について独自の感覚を養ってきました。
初対面でバッと一人になった時、「はじめまして、〇〇と申します」と、声のトーンや言い方、そして声の出し方(喉の奥から発声する感じ)など、総合的に「入り込める」雰囲気を作ることを心がけています。
これは、マニュアルや理論では説明できない、経験と勘に基づいたものです。 この場合、「自分で考えろ」という指導は、経験を積ませ、自ら考え、行動することを促すという意味で、ある程度有効です。 しかし、注意が必要です。
「自分で考えろ」指導の落とし穴
「正解が定まっていないもの」に対する「自分で考えろ」指導は、非常に繊細なものです。 単に「自分で考えろ」と放り投げるのではなく、適切なサポートとフィードバックが必要です。 以下に、よくある問題点を挙げます。
- 経験不足への配慮不足: 若手社員や未熟な人には、試行錯誤の機会を与えつつ、具体的なアドバイスやフォローが必要です。
- 曖昧な指示: 何をどう考えればいいのか、具体的な指示がないと、迷子になってしまいます。
- 無関心な態度: 「自分で考えろ」と言っただけで、その後一切関与しないのは、モチベーションを著しく低下させます。
- ノウハウチークへの陥り込み: 営業を科学するというアプローチは一見魅力的ですが、実際には「正解」がない領域においては、かえって不自然で、お客様に不快感を与えかねません。
効果的な「自分で考えろ」指導
では、「自分で考えろ」指導を効果的に行うにはどうすれば良いのでしょうか?
1. 正解が定まっているものと、定まっていないものを明確に区別する:
まず、問題の種類を明確に区別することが重要です。 正解が定まっているものについては、効率的に情報を提供するべきです。 一方、正解が定まっていないものについては、以下のポイントを意識しましょう。
2. 経験と思考、そして独自の感覚を重視する:
「自分で考えろ」指導の真の目的は、マニュアル通りの行動ではなく、個々の状況に合わせた柔軟な対応能力を養うことにあります。 長年の経験から培ってきた直感や感覚を大切にすることも重要です。
3. 長期的な視点と余裕を持つ:
「自分で考えろ」指導は、即効性があるものではありません。 時間と労力をかけ、じっくりと育成していく必要があることを理解しましょう。 特に、新規顧客との関係構築など、長期的な視点が必要な場面では、短期的な成果に固執せず、じっくりと育成に時間をかけることが重要です。
4. 環境とサポートの重要性:
「自分で考える」ための環境とサポートが不可欠です。 適切な情報提供、相談相手、そして失敗を許容する雰囲気を醸成することが重要です。 例えば、私の経験からすれば、上司から適切なアドバイスをもらえたこと、そして試行錯誤を許容する会社文化があったことが、自身の成長に大きく貢献しました。
5. 希望を託すこと:
特に、未熟な段階の部下や若手に対しては、「自分で考えろ」と言う前に、まず彼らの置かれている状況を理解する必要があります。彼らは、目の前の課題に精一杯取り組んでいるかもしれません。そんな時に「自分で考えろ」とだけ言うのではなく、まずは彼らが抱えている課題を理解し、その解決策を一緒に探る姿勢が大切です。彼らの潜在能力を開花させるには、まず「希望」を与えることが先決です。
事例:野村證券での経験
私は新卒で野村證券に入社しました。大企業ならではの、詳細なマニュアルとロープレといった指導体制が整っていました。しかし、実際には、お客様への提案方法や顧客対応に関する具体的なマニュアルは存在せず、先輩社員からの指導も「自分で考えろ」というものが多かったです。 最初は戸惑いましたが、この経験を通して、自ら考え、行動する大切さを学びました。
まとめ
「自分で考えろ」という指導は、一見厳しいように感じますが、適切な状況と方法で用いれば、非常に有効な教育方法となります。 しかし、それは、単なる「投げやり」ではなく、長期的な視点と、個々の状況に応じたサポートを伴うものであるべきです。 そして、その指導を受ける側にも、現状を打破しようとする強い意志と、将来を見据える余裕が不可欠です。
私の社会人経験から得た結論は、「自分で考える」という能力を育むには、時間軸を長く取り、個人の成長を丁寧に支援する必要があるということです。
最後に
社会人3年目頃までは、パソコンのシャットダウン方法すら分からず、電源ボタンを長押しして無理やり電源を落としていました。 皆さんも、自分の成長の過程で、そういった経験があるのではないでしょうか? 「自分で考えろ」という指導は、時に厳しいですが、自身の成長にとって不可欠な要素です。 ぜひ、この考え方を参考に、自身の成長に役立ててください。
