日本の城とヨーロッパの城塞都市:驚きの違いと、その背景にある歴史的・地理的要因
- 2024-12-14
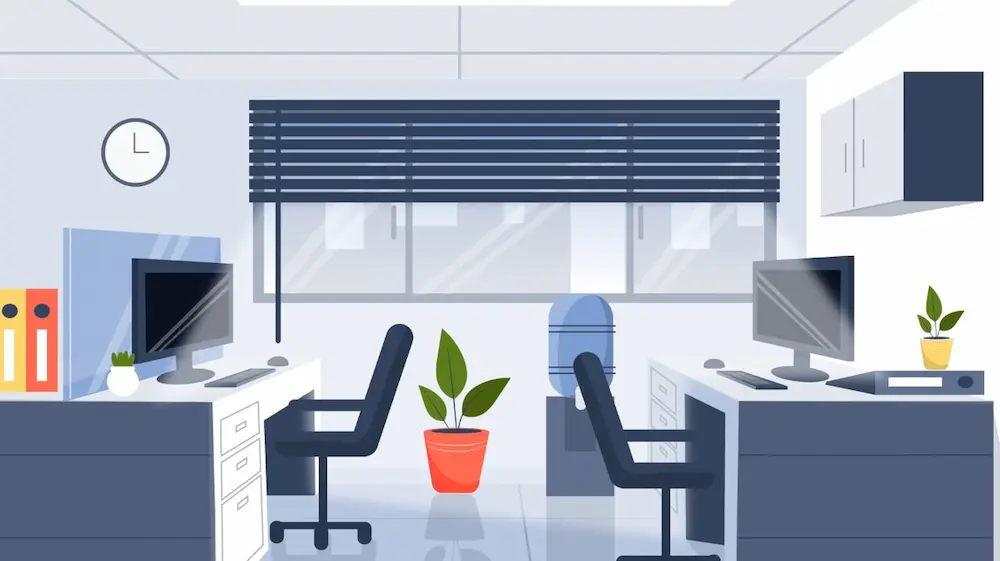
日本の城とヨーロッパの城塞都市:驚きの違いと、その背景にある歴史的・地理的要因
古来より人類は、領土を守るため様々な工夫を凝らしてきました。その結晶こそが「城」です。時代とともに進化を遂げてきた城ですが、日本とヨーロッパではその姿、そして城と町との関係に大きな違いが見られます。本記事では、両者の違いを比較検討し、その背景にある地理的要因や歴史的経緯を深く掘り下げていきます。
城の外観:東洋と西洋の対比
中世ヨーロッパの石造りの重厚な城と、日本の白く優美な天守閣を思い浮かべてみてください。その違いは一目瞭然です。ヨーロッパの城は城塞都市(城壁都市)の中心に位置し、町全体を高くて頑丈な城壁で囲うことで外部からの侵入を防いでいました。これはまさに、拠点の最終到達点と言えるでしょう。
しかし、多様な形の城を擁する日本では、ヨーロッパのような城塞都市は発達しませんでした。なぜでしょうか?日本の技術が遅れていたわけではありません。そこには、日本独自の複雑な要因が潜んでいるのです。本記事では、日本の城下町とヨーロッパの城塞都市を比較しながら、その違いを解き明かしていきます。
日本の城:多様な役割と巧みな防御戦略
日本の城は、大きく分けて4つの重要な役割を持っていました。
1. 軍事拠点としての機能
まず第一に挙げられるのは、軍事拠点としての役割です。非常時には敵の進攻を防ぎ、籠城戦の拠点となります。そのため、武器や食糧などの備蓄も城内に施されていました。
2. 権力の誇示と威圧効果
戦国時代の織田信長が築いた安土城は、それまでの城とは一線を画す圧倒的な存在感を放っていました。特に、類を見ない巨大な天守閣や、天守閣周囲を囲う石垣は、前例のない豪華絢爛なもので、たちまち話題になったそうです。安土城に住まう信長は、領民にとってまさに天上人のような存在として映ったことでしょう。中世において上下関係が曖昧だった時代、安土城のような威圧的な城は、主従関係を視覚的に示す重要な装置だったと言えるでしょう。また、敵の進攻意欲を挫く効果もあったと考えられます。この圧倒的な存在感は、後の権力者たちも競うように巨大な城を築いていくことになります。
3. 行政・政治の中枢
城内には御殿と呼ばれる建物が設けられ、城主や家臣が集まって政務を行う場所となりました。現代で言うところの県庁や役所に相当します。ちなみに、現在でも多くの城跡が公共施設として利用されている例があり、中世からの伝統が現代に続いているのかもしれません。
4. 城主とその家臣の生活空間
城は城主の住む場所として利用されていましたが、私たちが想像するような天守閣で生活していたわけではありません。天守閣は主に物置きとして使われ、城主の中には生涯一度も天守閣に上がらなかった人もいたほどです。実際の生活は本丸御殿や二ノ丸御殿といった、天守閣とは別の場所で営まれ、各国からの使節を迎える大接見間や会議用の広間なども備えられていました。
このように、日本の城は軍事拠点、権力の誇示、政治の中枢、そして生活空間という多様な目的を持って建てられていました。
ヨーロッパの城:侵略への備えとしての城塞都市
一方、ヨーロッパの城はどうだったのでしょうか?実は、ヨーロッパの城も日本の城と変わらぬ目的で建てられていました。要塞や軍の司令官の住居として、また政治や情報の拠点としての機能を備えていました。軍事拠点としては、山地や河川沿いなど交通・軍事上の要所に築かれ、支配地域の防衛の役割を担っていました。食糧・武器・資金の備蓄場所としても利用されていた点も共通です。
一見、全く異なる姿を持つ日本とヨーロッパの城ですが、軍事拠点、政治、生活という共通の目的を持っていたのです。では、なぜ同じ目的を持ちながら、これほど異なる形になったのでしょうか?
地理的条件:大陸と島国の違い
日本とヨーロッパの大きな違いは、食生活、天候など様々ありますが、根本的に異なる条件があります。それは地理的条件です。ヨーロッパはユーラシア大陸に位置し、日本は小さな島国です。この違いが、両国の防衛方法に大きな違いを生み出しました。
地図を見ても分かる通り、ヨーロッパは広大なユーラシア大陸にあります。大陸にあるということは、他国と陸続きであるということです。ヨーロッパ諸国は、ヨーロッパだけでなくアジアとも陸続きであり、常に異民族からの侵略の危機にさらされていました。そのため、人々は一箇所に集まり、高い城壁の中で生活せざるを得ませんでした。国民と領土を守るために、高く頑丈な城壁が築かれていたのです。ちょっとやそっとでは越えられそうにない城壁で町を囲むことで、侵略から身を守る必要があったわけです。
では、日本はどうでしょうか?ヨーロッパとは異なり、島国であるため周囲を海に囲まれています。そのため、海が城壁の役割を果たし、過去一度たりとも異民族からの侵略を許したことはありませんでした。例えば、1274年の元寇の時も、嵐が元軍を撤退させた一因と言われています。このように、国土自体が天然の要塞として機能していたため、高い城壁は必要なかったのです。
天高く馬肥ゆる秋:言葉が語る文化の違い
大陸と島国日本の違いを明確に感じさせる面白いエピソードがあります。「天高く馬肥ゆる秋」という言葉です。日本では、秋は空が高くなり、馬が肥えるほど食べ物も美味しい豊かな季節という意味で使われます。しかし、この言葉の発祥地である中国では、全く異なる意味を持ちます。実は、「越えた蒙古馬に乗った北方民族が秋の収穫期に襲来する」という警戒信号だったのです。これが平和な日本に伝わるうちに意味が変わっていったとされています。
常に異民族の侵略に目を光らせなければいけなかった大陸と、日本の危機感の違いが表れています。このようなエピソードからも分かるように、異民族による侵略の心配がない日本では、高い城壁は築かれませでした。
地震国日本:高い城壁の建設困難
しかし、高い城壁を作らなかった理由はそれだけではありません。他にどのような理由があるかというと、地震です。日本は地震大国であるため、高い城壁を築いても地震の度に崩れてしまい、非常に危険だったのです。これに対し、地震の少ない西洋では高い城壁を築くことが可能でした。このことから、日本は城壁を作らなかったというより、作れなかったという見方もできますね。
日本の防御:堀と城下町の総合防衛システム
他民族からの侵略がないにしても、国内での紛争は絶えずありました。では、高い城壁がないのにどうやって城を守っていたのでしょうか?そのヒントは「城」という漢字にあります。「城」は「土から成る」と書きますね。日本の城は、まさにこの字の通り、土を掘って堀を作り、その土で壁を築きました。日本の城の防衛は、堀が要でした。
堀とは、城の周囲を囲むように掘られた溝のことです。簡単に越えられない深い溝に、さらに水が張られたものもあり、その深い溝や水が城への侵入を妨げました。このような防衛方法は古代より既にみられたと言います。中世の城で特に有名なのは姫路城の堀でしょう。30にも及ぶ堀は、なんと城下町一体を囲むように作られていました。このように、城下町も含めて堀で囲んだ都市造りのことを総構えと言います。戦国時代後期からこの防衛方法をとる都市が増えました。総構え規模の大きな城としては、大阪城や江戸城も有名です。特に、豊臣秀吉が築いた大阪城の堀は、一辺2km、総計8kmに及ぶ大規模な総構えで、難攻不落として知られていました。この総構えが最も活躍したのは、1614年に起こった大阪冬の陣です。徳川家康は大阪城に攻め込みましたが、20万もの軍勢を持ってしても城を落とすことができませんでした。そのため、家康は和議の条件として総構えの破壊を要求したほどです。それほど、総構えの威力は絶大だったと言えるでしょう。
こう聞くと、「日本の総構え、ヨーロッパの高い城壁と一緒じゃないか?」と思いませんでしたか?都市を堀で囲むのは、城壁で囲むことと変わらなく感じますね。しかし、ヨーロッパの城塞都市とは決定的な違いがあります。それは、日本の総構えは外側に行くほど貧弱になるという点です。ヨーロッパでは都市を囲む外側の城壁を最も強固に築くのに対し、日本は城下町を守る堀は城を守る堀より簡素なもので、城に近い中心部に行くほど強固でした。都市部の防御が貧弱だったのは、異民族からの侵略の心配がない日本では、民家や都市が侵略の標的になることは少なかったからだと言われています。このような背景から、都市と住民を守るという発想が育ちにくかったため、城を攻めにくくしつつも都市部の防御自体は薄かったと考えられています。
こうした防衛の要であった堀ですが、人力で掘ったものだけでなく、自然の地形を巧みに利用したものも存在します。その多くは豊富な水を活用することで防御力を高めていました。例えば、河岸段丘と呼ばれる川の流に沿って階段状になっている地形の崖の上に城を建てることで、高低差により自然の防御が可能でした。また、川の水を引き込んで堀の代わりにする、沼地や湿地を利用して敵の行動を制限する城もありました。その代表例が、真田昌幸によって長野県上田市に築かれた上田城です。巧みに川の流れを引き込むことで、徳川軍の二度にも渡る侵攻を跳ね返したことでも知られています。現在も城跡の崖に残る、高さ12m以上の断崖は、まさに難攻不落であったことが伺い知れます。また、長篠の戦いの舞台となった長篠城も、川と崖を利用した防衛の好例でしょう。場所は愛知縣新城市、寒狭川と豊川のちょうど合流地点に存在する河岸段丘の段差の上に築かれた長篠城は、厳しい天然の要塞となっていました。その防御力は素晴らしく、なんと長篠城兵500人に対して武田軍は1万5000人いたにもかかわらず、攻め落とすことはできませんでした。
城下町の総合防衛システム
堀での防御以外にも、城を守る仕組みがあります。実は、城下町全体が防御システムとして機能していたのです。
まず第一の防御として、城の近くには上級武士、その外側に下級武士を住まわせる武家地を配置しました。こうすることで有事の際にすぐに城に駆けつけて参戦できます。さらに武家地の外側には商人や職人などの町人地を作り、城下町の最外側には強固な造りの神社や寺を置き、侵入を難しくする計画的な配置がなされました。建物は隙間なく建てられ、要所には堀や門、街道も設けることで防御力を高めたそうです。その上、多くの城下町では道路に工夫が凝らされていました。カクカクと曲がる「鍵の手」と呼ばれる道や、行き止まり、袋小路、あえて進攻方向にまっすぐ進めないようにした食い違いなど、複雑な道によって敵が城に近づくことを困難にしたのです。あなたの住む町でも見たことがあるのではないでしょうか?「なんでわざわざ行き止まりを作るんだろう?」と思われたことがあるかもしれません。確かにこの入り組んだ構造は交通の面では不便でしたが、防御には極めて効果的でした。
ちなみに、こうした地形を生かした防御はヨーロッパでも行われていました。例えば、12世紀のシリア、トルトゥーズ城では、沿岸部という立地を生かしています。内陸部の城では井戸や小川から堀に水を引くのが一般的だったのに対し、ここでは20もの堀に上流から水を引いていました。さらに極端な例を挙げると、シリアのクラク・デ・シュヴァリエ城には、世界でも最も規模の大きな堀があります。なんと城の土台部分をのこして周囲をぐるりと削り取り、幅18メートルもの堀で城を孤立させてしまったのです。まるで柱状の土台の上にポツンと建つ城は、橋をかけなければ近づくことすらできない要塞となりました。地形を生かした防御は、日本のみならず世界中で考えられていたと言えるでしょう。
このように、ヨーロッパと違い高い城壁が作れない日本の城では、堀や地形の利用、そして城下町全体を使った総合的な防御システムを発展させていきました。
城での暮らし:衛生管理の対比
生活をする上で重要な要素、それは衛生です。日本とヨーロッパの城を衛生面から比較してみると、面白いことが見えてきます。特にトイレ事情の違いは、非常に顕著に表れていました。
まず日本の城のトイレ事情ですが、そもそも日本の城ではトイレの設置そのものが極めて限定的でした。例えば、姫路城では天守閣の地下に2つのトイレが確認されているだけ、他の櫓には一箇所もトイレが設置されていません。さらに面白いことに、この天守閣のトイレにも3つの備前焼の落し壷が設置されていたものの、昭和に天守閣を大修理した際の調査で、使用された形跡が全くないことが判明しました。なぜ、せっかく作ったトイレを使わなかったのでしょうか?
この理由は、当時の日本の城では衛生管理が極めて重視されていたことに関係しています。現代のような効果的な消毒薬もない時代、トイレの排泄物が原因で疫病が蔓延すれば取り返しのつかない事態になりかねません。そこで考え出された解決策が、おまるの使用です。城中ではおまるを使い、排泄物はすぐに城外へ運び出して処分するようにしていたと言われています。トイレの下に設置した大きな壷を動かすのは大変ですが、この方法なら大した手間をかけることなく城内を清潔に保つことができたのです。この衛生管理の徹底ぶりは、当時の城の掟からも伺い知ることができます。例えば、1581年には、御法度書が小田原城においてトイレに関する規定を設けました。その内容は、「馬の糞尿は毎日城外に処分し、遠くへ捨てるように定める」ものです。また、翌年には足軽城でも同様の規定を設け、人や馬の糞尿を一日以上放置することを禁じました。
一方、ヨーロッパの城のトイレは全く異なる発展を遂げていました。13世紀頃からは、イギリスやフランスの城に「ガードローブ」と呼ばれる特徴的なトイレが設置されるようになります。これは、城壁から張り出した場所に設置されていました。このガードローブには、信じられないような名残が存在します。その名残とは、排泄物の蓄積がハエなどを誘致し、様々な食中毒を増やすというものです。そのため、なんと中世のイギリスではこのガードローブに一丁羅を吊るして保管していたというから驚きです。ちなみに現代ではタンスなどのことをワードローブと言いますが、ガードローブがその語源となっています。このガードローブは城内の様々な場所に設置されており、その存在は建物の特徴からも容易に確認できました。それは、ガードローブがある城壁部分には排水用の通気孔があり、またトイレのある階には張り出し部分があるのですぐにわかります。このガードローブの仕組みはとてもシンプルで、排泄物を城の外に自然落下させることが分かるようになっています。他には金属製のシュートを通して地下の排水溝に落とすパターンもありましたが、基本的には城外の堀に落とされるか、そのまま地面にころがり落ちる仕組みでした。これらの汚物は後に業者によって処理されたと言われています。なお、シュートを使ったトイレには、思わぬ弱点になることもありました。13世紀のフランス、ガイアール城やウズベキスタンにあったアルク城の包囲戦では、このシュートを利用して敵が城内に侵入する事件が起こっているのです。
これに関しては、当時の攻め手の執念に拍手を送っておきましょう。
城のトイレ事情:量と質の違い
このように日本とは全く異なる仕組みを持っていたヨーロッパのトイレですが、設置数ははどうだったのでしょうか。やはりその数も日本とは大きく異なっているようです。ヨーロッパでは、城内のトイレは使用者に応じて数を多く配置しました。その種類も豊富で、城主の家族用、来賓用、守備兵用、惣寮用などが存在します。設置のされ方も現代に通じるものがあり、当時の主衛兵用トイレは複数の便座が横並び、背中合わせに設置されていたそうです。また、城主的トイレは広間や城主的寝室の近くの通路に設置されていましたが、狭い回廊を通っていく必要がありました。これは防衛上の対策だったと考えられます。衛生対策としては、虫対策として換気用の窓が設けられている他、木製のドアで仕切られていた、使用後は鉢や水差しで手を洗う習慣もあったそうで、ほぼ現代の私たちと同じような造りのトイレだったようです。
このように、日本とヨーロッパの城では、トイレに対する考え方や対策方法が大きく異なっていました。日本が徹底的な衛生管理を重視したのに対し、ヨーロッパは実用的な設備を整備していたと言えるのではないでしょうか。しかし、トイレの違いは表層の一角に過ぎません。もう一つ衛生管理に関して対照的な違いがあります。それは、城内の清潔さを保つための方法です。
城内の衛生管理:徹底的な清掃と草臥れた床
まず日本の衛生管理ですが、城内は城外に比べて狭い空間ですよね。そこに大勢の人々が長期間密集していれば、当然のことながら汚れが蓄積していきます。日本では古代より、たびたび発疹チフスなどの疫病が流行した苦い経験から、汚れを放置することが病気につながることを知っていました。そこで日本の城では、徹底的な清掃が日常として確立していきます。特に印象的なのは、先ほどのトイレの規定でも登場した御法度書の取り組みです。御法度書が作成した小田原城の規定には「毎日、各部屋の掃除を厳密に行うべきだ」という規定がありました。部屋とは城内の区画のことで、この規定は自分の所属する部屋をよく掃除するように指示するものです。この他にも御法度書の城郭関係資料には「掃除」という言葉が頻繁に登場するほど、清潔さへの意識は徹底していたようです。
一方、ヨーロッパの城の衛生管理は日本とは全く意識が異なります。まず、中世の城の床にはあるものが散らばっていました。それは何かというと、藺草や藁です。当時のヨーロッパでは、カーペットの代わりに藁などを敷くのが一般的でした。そして問題だったのは、このカーペットの交換頻度です。これらの清掃と交換はメイドの仕事でしたが、その頻度は城主に好みによってまちまちでした。月ごとに交換する城もあれば、季節ごと、さらには年に一度しか交換しない城もあったと言います。
この衛生管理のずさんさは、15世紀の偉大な学者エラスムスの手紙からも生々しく伝わってきます。彼によると、床の藺草は時々張り替えられるものの適当な材料だったため、下層部分は20年も放置され、そこには痰や嘔吐物、人や犬の排泄物、ビールや魚の残骸など様々なゴミが堆積していたというのです。そして天候の変化とともに、その床から瘴気が発生し、健康に極めて有害だとエラスムスは警告していました。また、建築上の問題から窓が少なく換気がしにくいという点も問題でした。するとその後、さすがにこの状況はまずいと改善案として藺草や藁を編んだマットが導入されました。これは床を掃除する際に外に出して叩くことができる便利な物です。さらに悪臭対策として、マットにはラベンダーやカモミール、バラの花びら、ミントなどの香りの高いハーブが散りばめられていました。ただ、このマットはとても快適そうですが、城主の中には藁が散らばった見た目を好むものもいたようで、導入しない城も多くあったようです。
城の暮らしやすさ:寒さとの戦い
こうした衛生管理以外にも、ヨーロッパの城には別の問題がありました。それは建物自体の構造に起因する暗さと寒さです。先ほど換気の問題でも触れた窓にも起因する問題ですね。中世ヨーロッパの城は強固な防御のために石造りが基本でしたが、当時の建築技術では大きな窓を設けることができませんでした。その結果、厚い石壁は太陽の光で十分に暖められず、部屋は常に暗く寒い状態が続いたのです。ですが、この問題は12世紀後半以降、建築技術の発展とゴシック様式の導入により改善されていきます。ゴシック様式とは、天井を三角形のようなとがった形状にすることで、壁を薄く、建物をより高く作れるようになった建築方法です。それまでのロマネスク様式で必要だった多数の石材が必要なくなったことで、より大きな窓を持つ明るい部屋が設計できるようになりました。
しかし、まだ寒さの問題が残っています。驚くべきことに暖炉は12世紀中盤まで存在せず、それまでは囲炉裏のような直接火で城を暖めていました。これでは熱が効果的に拡散せず、その上大量の煙が発生する始末です。それを解決する暖炉が登場しても、排煙装置をつける大掛かりな工事は難しかったため普及には時間がかかったようです。ただし、この寒さの問題は、ヨーロッパだけでなく日本の城にもありました。当時は効果的な断熱材などはありませんし、暖炉もありません。そのため、伝統的な囲炉裏や湯たんぽ、どてらなどの防寒具で寒さに耐えていたようです。
日本とヨーロッパの城:根本的な考え方の違い
このように、日本とヨーロッパの城では、根本的な考え方の違いが暮らしやすさの違いを生んでいました。ヨーロッパの城では、トイレや暖炉などを始め、より便利な設備の充実力を入れていましたが、衛生管理はずさんなものでした。対して日本の城は、衛生管理に重点を置くことで健康に暮らすことに力を入れていましたが、その反面トイレや寒さ対策には若干不便もあったようです。このように城での暮らしを単に見るだけで、日本とヨーロッパの文化的違いが如実に体感できて面白いですね。
オダワラ城と城塞都市への挑戦:そして平和の礎
さて、これまでヨーロッパの城塞都市、日本の城と城下町の様々な違いを楽しんできましたが、実は日本にも一度だけヨーロッパ型の城塞都市を目指した野心的な試みがあったと言われています。その試みは、戦国時代末期の小田原で起こりました。当時の小田原といえば東日本で最大の都市ですが、一体何が起こり、どのような結末を迎えたのでしょうか?
オダワラ城の総構えと、その戦略的意義
時は16世紀の戦国時代。後北条氏が治める小田原城は、無敵の城としてその名を轟かせていました。あの上杉謙信や武田信玄の攻撃にも耐えた難攻不落の城です。ですが、16世紀も終わり頃、豊臣秀吉が攻めてくることを察知した後北条氏は、前例のない大規模な防衛計画を実行に移します。それは、総構えの建設でした。総構えとは、先ほどご紹介した通り、城下町ごと堀で囲むことです。その規模はそれまでの総構えとは一線を画す、まさに壮大なものでした。なんと、丘陵部から海岸線まで、周囲約9kmにも及ぶ防御線が築かれたのです。堀は上幅が20~30m、深さが10~15mという驚くべき規模で、さらにその内側には土塁と呼ばれる土を盛り上げて堤防のようにした防御設備が設けられていました。驚くのはそれだけではありません。堀の構造も画期的なものでした。近年の発掘調査により、堀の斜面は曲線状で、そこに「障子堀」と呼ばれる特殊な仕掛けが施されていたことが分かっています。これは高さ2mほどの小壁を敢えて堀に残すもので、堀底に落ちた敵の動きを封じる巧妙な防御システムでした。ここまで規模が大きくなると町にも簡単に侵入できず、もはや堀ではなく壁、まさにヨーロッパの城塞都市ですよね。これまで日本では、城の防御は頑丈だが城下町の防御は貧弱であるのが当たり前でした。そのためこの小田原城の試みは、実に革新的なものだったわけです。なお、後北条氏が海外の事例を知っていたかは不明です。ただ、その作りは海外の城塞都市と非常に似通っていたことは間違いありません。しかし、なぜ後北条氏はそもそも城下町ごと防御しようとしたのでしょうか?その理由は、当時の小田原の城下町の規模にあります。東日本で最大の都市であった小田原城下町には、食糧や兵器、武器を扱う商人たちが集まり、日用品から武器まで様々な職人が技を競っていました。そして争いが長期戦となれば、これらの職人たちの存在は不可欠です。さらに、城壁の内側には広大な田畑も含まれており、食糧・武器などの戦争に必要な物資の調達が城内の都市だけで可能な状態でした。こうしたインフラを支える民衆を一緒に保護することで、城自体の防御力を上げる狙いがあったのです。実際に秀吉軍による包囲の際には、多くの農民たちもこの中に避難したと伝えられています。この小田原城の城塞都市への挑戦は、日本の城郭史に新たな可能性を開いたはずです。しかし、どうやら現代に至るまで、日本には城塞都市が誕生することはなかったようです。一体なぜなのでしょうか?その背景には、ある人物による巧妙な政治戦略が隠されていたと言われています。
秀吉の天下統一戦略と城塞都市の消滅
小田原城が城塞都市になりきらないうちに、秀吉が20万もの軍勢を引き連れて小田原征伐に乗り出しました。対する小田原城の軍勢はわずか3万4000。この圧倒的な戦力差で、すぐに降伏すると思われた小田原城ですが、なんと3ヶ月間の包囲戦を実質引き分けに持ち込みます。それは、小田原城は最終的に落城したものの、戦闘による敗北ではなく、策略、つまり話し合いによる開城だったからです。この事実は、城塞都市が防御戦において極めて有効であることを明確に示し、戦国武将たちに大きな衝撃を与えました。特に注目されたのは、一般市民を城壁内に籠城させ、武士と共に戦う戦略です。後北条氏は秀吉の進攻に備え、15歳から70歳の男子を対象にした徴兵を行っていました。
こうした一般市民の戦争への参加は、戦国時代後期には防御力を弱めるとして避けられる傾向にありましたが、むしろ強化することが実証されたわけです。この戦略の有効性は、特に小田原征伐の過程で起こった御所城の攻防戦にも見られます。現在の埼玉県行田市にあった御所城は、後北条氏の家臣である成田氏長の居城でした。小田原征伐に伴い、この御所城も攻撃の対象となりましたが、城主である成田氏長は既に小田原の戦に向かっていたため、城主不在での籠城戦となりました。「さすがに城主不在ではすぐに降伏するだろう」と思いきや、なんと少年や女性を含む多くの民衆が徹底して自らの持ち場を守り抜いたというのです。その抵抗は凄まじく、信じられないことに小田原が落城した後もなお抵抗し、降伏することはありませんでした。最終的に小田原にいた城主的官告で降伏するまで抵抗を続けたというから驚きです。この御所城はもともと周囲を沼地に囲まれた堅固な城ではありましたが、城主不在という不利な状況で籠城を続けられた背景には、武士だけでなく農民や職人、商人、惣寮、さらには女子供までもが一丸となった地域共同体の結束があったからでしょう。
民衆が共に戦った事例でもう一つ印象的なものがあります。それは九州の城村城の抗戦です。1587年、熊本県山鹿市にある城村城は、秀吉による九州征伐をなし遂げた佐々成政の軍勢相手に一揆を起こします。城主隈部親泰の指揮のもと、男約8000人、女約7000人という大規模な籠城戦が展開されました。この戦の特徴は、うち武士がわずか800人程度だったことです。戦いに参加したもののほとんどが一般の農民や町人、惣寮でした。彼らは鉄砲830挺、弓500張りという武器で武装し、実に7ヶ月もの間降伏することなく戦い抜いています。城自体は小田原城のような総構えではありませんでしたが、市民を含めた総力戦を展開することで、強力な防御力を発揮しました。しかし、この城村城の抗戦が日本の城塞都市の未来を大きく変えてしまうことになったと言われているのです。
城村城の一揆と、秀吉の天下統一政策
この城村城で起こった一揆の報告は、北野の大茶会を始めたばかりの秀吉の耳に入りました。そして皮肉なことに、この茶会は秀吉の九州制圧を世に広めるために開かれたものでした。にもかかわらず、「九州で反乱が起こっている?九州制圧とは?」こうして面子を潰されてしまった秀吉は、当初計画していた茶会を一日で中止し、民衆一体となった防御と、これからできるであろう城塞都市への対策を練り始めたと言われています。そしてその1ヶ月後に打ち出した対策、それが兵農分離の完全実施と刀狩りの命令でした。
兵農分離とは、武士と町人の社会的役割を完全に分ける身分制度です。またそれに伴い行われた刀狩りは、武士以外の身分の者には武器を放棄させるものでした。秀吉は、城塞都市の発展が今後の統治にとって大きな脅威となることを察知しており、都市の城塞化を防ぐには兵農分離が不可欠だと考えていました。とはいっても秀吉は兵農分離を進めた一方で、強固な城壁のような防御施設の建設自体は禁止していません。小田原攻略後も総構えの撤去を命じることはなく、各地での総構えを作る工事も黙認しています。城塞都市化が懸念事項であるならば、それと同じ性質を持つ総構えを禁止すべきではないかと考えますが、秀吉はそれよりも人々の身分を区別する兵農分離を重視していました。それは、彼にとって重要だったのが目に見える城壁や堀ではなく、目に見えない社会体制の変革だったからです。
これまでの事例から、城塞都市の防御に最も必要なのは民衆の協力だと秀吉は見抜いていたのです。そのため、武士と農民・町人の社会的役割が明確に分離されれば、たとえ城塞都市の形を取っていても市民の戦闘協力は実現しない、と秀吉は考えていたのです。そしてその読みは見事に的中します。例えば、滋賀県大津市にあった淀城の攻防戦では、京都の町人が寺院の高みに拠点を構えながら戦いを牽制する様子が見られました。これは、民衆の精神が変化し、戦争は武士が行うものという意識に変わったことを示しています。ただし、この変化は完全なものでもなかったようです。秀吉死後の大阪の陣における大阪城の籠城戦では、これまでと同様に多くの一般市民が参加しています。これは、戦う当事者への感情によって市民の協力態度が変化したことを示しているでしょう。籠城できない相手には防衛者となり、共感できる側には積極的に協力する、というより主体的な判断も戦場に影響したということです。
まとめ:日本の城と城塞都市の軌跡
このように、城塞都市が日本で発展しなかった背景には、秀吉による巧妙な社会改革がありました。兵農分離という政策は、単なる物理的な制限のみならず、人々の意識を変えることで城塞都市の可能性を封じ込めたのです。こうして日本では、ついぞ城塞都市が発達することはありませんでした。地理上の違いにより全く異なる発展を遂げた日本とヨーロッパの城と町。何かが一つ違えば、日本でも城塞都市が発達していたかもしれない。そんなことに思いを馳せられるのが歴史の面白いところですね。世界の歴史はまだ謎に包まれています。これからも一緒に、世界の謎をのぞく旅に出ましょう。それでは次の旅でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
