幕末日本の影に潜むイギリスの金融戦略:アヘン戦争から明治維新まで
- 2025-01-03
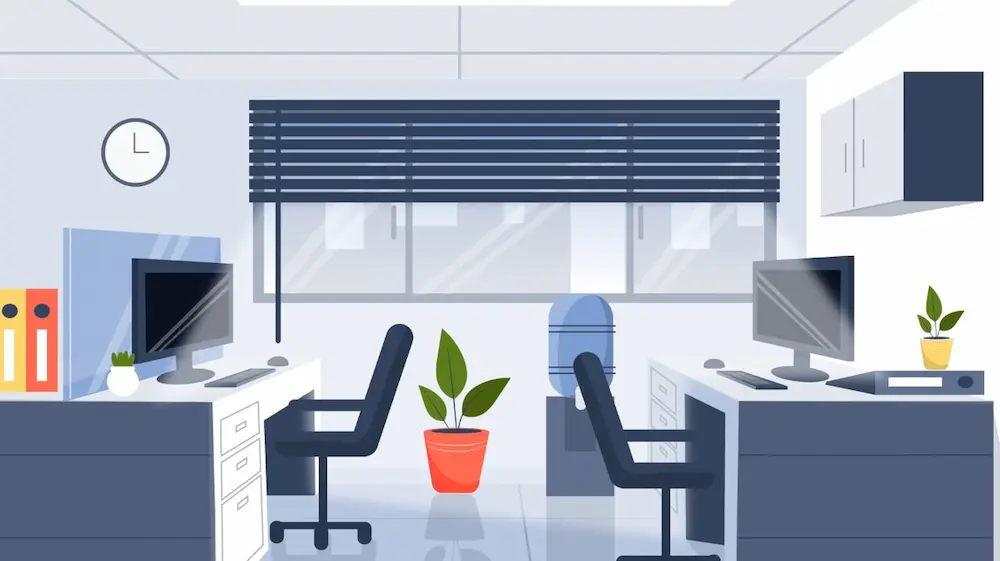
幕末日本の影に潜むイギリスの金融戦略:アヘン戦争から明治維新まで
18世紀後半、ヨーロッパでは国民国家が次々と誕生し、近代化が急速に進みました。その先駆けとなったイギリスは産業革命によって大量生産された安価な製品を世界中に輸出しました。では、具体的にどこで売られたのでしょうか?
未開拓市場:アフリカとアジア
イギリス製品の捌け口となったのは、国民国家が未成立だったアフリカやアジアといった未開拓市場でした。「遅れた地域に近代文明を教えよう」という大義名分の下、西洋諸国の植民地化が始まりました。
日本も例外ではなく、幕末期には何度も外国船の来航・偵察を受けました。特に注目すべきは、当時覇権国家であったイギリスです。同じ島国であるイギリスは、いかにして覇権を握り、日本やアジアに接近したのでしょうか?
イギリスの覇権戦略:金融の動き
その鍵は、マネーの動き、金融にありました。歴史的に世界の貿易決済に使われた通貨は銀(シルバー)でした。中世までは南ドイツの銀山を保有したアウクスブルクのフッガー家が欧州金融の中心でしたが、新大陸でポトシ銀山やサカテカス銀山を発見したスペインが中心となります。やがてスペインは「大洋の沈まぬ国」と呼ばれ、栄華を極めました。
では、銀山を持たなかったイギリスはどのように金融の中心へと成り上がったのでしょうか?
ロスチャイルド家:銀行業の巨匠
世界の金融を語る上で外せないのが、銀行業で財を成したロスチャイルド家です。初代マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドは1763年、フランクフルトで諸侯やロシアの古銭を販売する古銭商を始め、貴族の顧客を獲得。やがて貴族の投資アドバイザーとなり、資産家へと成長しました。
彼は5人の息子をフランクフルト、パリ、ウィーン、ナポリ、そしてロンドンに分散させ、銀行業を開業させました。分散させた理由は、リスク分散と情報ネットワークの確立です。
ナポレオン戦争とロスチャイルド家の戦略
杉田玄白や伊能忠敬が活躍した1815年、欧州ではナポレオン最後の戦い、ワーテルローの戦いが起こっていました。リスク分散を欠かさないロスチャイルド家は、パリのロスチャイルド家がナポレオン率いるフランスに投資、ロンドンのロスチャイルド家ネイサンはイギリスに投資しました。
さらにネイサンはイギリス敗戦の偽情報を大々的に流して、イギリス国債を暴落させました。それは、暴落した国債を最安値で買い占めるためです。結果、ナポレオンのフランスが敗れ、イギリスが勝利を収めました。偽情報を操ったネイサンも大勝利です。
ネイサンは、その幅広いネットワークでナポレオンが不利であること、そして敗戦することを知っていたのです。こうしてネイサンはナポレオン戦争で巨万の富を得て、イギリス金融を動かす資金源を築き上げました。
金融と世界の覇権:銀から金へ
さらにネイサンの息子ライオネルは、当時ロスチャイルド家とズブズブだったディズレーリ首相に資金を提供し、エジプト総督からスエズ運河会社の株式を買い集めました。金融のみならず政界でも影響力をつけていったのです。
この頃、国際通貨のシルバーは銀山の開発が進みすぎた結果、過剰供給となり価値が下がりつつありました。つまり、銀山を持たないイギリスに有利な状況が生まれつつあったのです。
次に注目が集まったのは、よりレアな金属、ゴールドです。ロスチャイルド家などの資本家は、貿易決済や投資の利回りをシルバーからゴールドに変えました。金本位制を開発したのです。これは、イギリスの通貨ポンドを一定の重さのゴールドと交換できるというシステムです。ポンドとゴールド双方の価値を担保し、ゴールド時代、そしてポンドも信用される時代を作り上げたのです。
しかし、金本位制を確立するには、ポンドと同等の量の大量のゴールドが必要です。そこでイギリスはカリフォルニアや南アフリカの金鉱に莫大な投資を行いました。こうして世界のゴールドを一挙にイギリスへ集めたのです。結果、銀山なきイギリスはゴールドの力で金融の中心へと成り上がったのです。さらに大西洋三角貿易を確立し、西アフリカの奴隷をアメリカの植民地に輸出することで巨額の利益を上げました。
アヘン戦争と自由貿易帝国主義
少し時代を戻して、新アジアとの貿易はシルバー決済のままでした。すると、溜まるゴールドとは対照的に、インド産綿布と中国の紅茶の輸入拡大によりシルバーがどんどん流出し、貿易赤字となりました。銀山がないイギリスにはシルバーの蓄積はあまりありません。
この赤字解消のため、まず綿布を国産化しました。これが産業革命です。大量生産した安価な綿布を逆に需要の多いインドへ売りつけました。結果、インドの主産業は壊滅、経済は衰退し、ついにはインドはイギリスの植民地となりました。
次に狙われたのは中国です。茶は寒帯のイギリスでは栽培が難しいため、綿布のように自国生産はできません。そこで、貿易赤字解消のため目をつけたのが**アヘン(麻薬)**でした。植民地となったインド産のアヘンを中国へ密輸し、内部から破壊したのです。
アヘンが蔓延した中国はアヘンの販売を禁止し、イギリス商人が持っていたアヘンを没収しました。イギリスはこれを財産権の侵害、自由貿易の阻害として反発。こうして1840年、アヘン戦争が始まりました。明治維新の28年前です。
このアヘン戦争でイギリスは圧勝。南京条約で中国は香港等の割譲、2100万ドルの賠償金、広州、福州、廈門、寧波、上海の開港を認め、貿易の自由化を約束しました。このアヘン戦争によって、アジアでの恐ろしいシステムが完成します。自由貿易的帝国主義システムです。中国を植民地にはしませんでしたが、不平等条約を締結されイギリスに搾取されます。中国は国内経済の中枢、紙幣発行権と外交経済の中枢、関税をイギリスに握られたのです。
このように、領土を奪わず、市場を奪うやり方が自由貿易的帝国主義です。当時のイギリス経済学者アダム・スミスらは、自由貿易こそが世界を豊かにする方法だと発表しました。農業国も工業国も自由に貿易し合えば、市場が活発になりみんな幸せになると説いたのです。
アメリカ学派と保護主義
これに反発したのがアメリカの経済学者、アメリカ学派でした。中国を見れば一目瞭然です。自由貿易の元でイギリスに搾取されることを拒否しました。アメリカ学派は逆に関税を築き上げて国内産業を守る保護主義システムを主張しました。これをアメリカ北部のエイブラハム・リンカーンは採用。一方の南部はイギリス式の大量生産貿易企業、つまりは奴隷を用いた自由貿易システムを捨てられず、北部と対立しました。これが幕末の1861年にアメリカで起きた南北戦争の火種となったのです。
アメリカはイギリスの自由貿易の危険性を後の新政府主要メンバーに伝えていたようです。親日外国人としてアメリカから招聘されたエラズマス・ヘーシー・スミスは反自由主義、アメリカ学派です。さらに日米修好通商条約を結んだアメリカ全権タウンゼント・ハリスもアメリカ学派。アヘンを禁止させ、アメリカ式の高関税をかけて日本の産業を守る保護主義を推奨しました。
なぜアメリカは日本にここまでしてくれたのでしょうか?理由は、中国を支配するイギリスへの牽制です。中国から日本へ進出、そのまま太平洋から挟み撃ちされることを嫌ったのです。このように米英は幕末期に見えない経済戦争を行っていたのです。
実際アメリカも中国で暴れましたが、それはまた別の動画でお話しします。アメリカの策略もむなしく、1864年の四国艦隊下関砲撃事件の際には賠償金の支払いを減額する代わりに関税率を引き下げてしまいました。さらにイギリス公使ハリー・パークスは1866年の江戸条約でさらに関税率を引き下げています。関税が下がったことでヨーロッパの安価な製品が大量に輸入されました。これをうけて日本の国内産業は大ダメージを受け、財政はずるずる悪化したのです。
幕末日本がとるべき戦略
では、幕末の日本が欧米列強による植民地支配を防ぐためにすべきことは何でしょうか?
- まずは軍備を整えること
- その軍事費を捻出するために国力をつけること
- その国力を付けるために、欧米列強の最新技術を学ぶこと(近代化すること)
これが新政府、明治政府主脳の考えで、後の富国強兵、殖産興業につながります。とはいえ、1863年の薩英戦争や四国艦隊下関砲撃事件の経験から、倒幕の中心となる薩摩・長州藩は、幕府の中心となる薩摩・長州藩は、海外勢力の排除の考えの無謀さと幕府の能力のなさを痛感しました。これが倒幕運動を引き起こし、明治維新を完成させたのです。そして明治維新成功には、やはりイギリスが絡んでいたようです。
この頃のイギリス商社のうち、アヘン貿易や奴隷貿易を行った会社の1つにスコットランド系のジャーディン・マセソン商会があります。この会社はアヘン利権で成長した経緯があり、アヘン戦争開戦させた会社でもあります。アヘン戦争後は香港に進出、その後日本にも横浜支店を置きました。このジャーディン・マセソン商会の長崎代理店をしていたのが、1859年来日したあのグラバー率いるグラバー商会です。ちなみにグラバーもスコットランド出身です。
グラバー商会は開国したばかりの日本で絹糸やお茶の輸出を行いました。しかし、1863年8月18日の生麦事件には武器弾薬の輸入も行い、武器商人の顔も持ちました。また坂本龍馬とも繋がりがあり、倒幕に深く関わっています。グラバー商会は薩摩藩の五代友厚、森有礼、長州藩の伊藤博文、井上馨らの留学を援助しました。彼らはジャーディン・マセソン商会の横浜支店からイギリスへと旅立ったのです。このようにグラバーは後の政府重役を育成し、武器商人として薩長側の資金、物資援助を行なったのです。
結果として、このイギリスマネーの見えない力が明治維新を成功に導きました。しかし、リスク管理を徹底するのがロスチャイルド家です。薩長は目に見えてイギリスが支援しましたが、幕府を支援したのはフランスでした。そのフランスのトップはナポレオン3世。つまり、パリのロスチャイルド家はナポレオン3世の資金源となっていた可能性があり、結局敗後にはロスチャイルド家がいるように思えます。ちなみにペリーの黒船の息子オーガスタス・ベルモントはニューヨークで債権回収などを行ったロスチャイルド家の代理人です。ペリー来航計画の背景にもロスチャイルド家の存在があったのです。
岩倉使節団と明治日本の選択
さて、国内の様子を見てみると、倒幕後の1871年、岩倉使節団が欧米留学に出発しました。国の基礎固めと近代化のため、岩倉具視を団長とする若き留学僧計107名が欧米12ヶ国を訪問したのです。かかった費用は約100万円、現在の価値で約63億円をかけた大プロジェクトです。参加最年少は津田梅子の6歳。6歳で先進列強国を見て回った津田は後に津田塾を創設し、伊藤博文とも深い交流を持ちました。
最初に訪問したアメリカでは大歓迎を受けました。イギリスを牽制するアメリカは、日本にイギリスの悪巧みを教えたのかもしれません。次の欧州訪問ではイギリス、フランスで議会制を学びました。プロイセンでは宰相ビスマルクから「国際問題は国際法や条約ではなく鉄と血によってのみ解決される。日本が無反論すべきは君主権が大きく軍事的力の強い我々プロイセンだ」と告げられ、一行は感銘を受けました。この頃から日本の主脳にはドイツがちらつくようになります。
帰国途中に付いた一行はスリランカ、シンガポール、サイゴン、香港、上海を経由して列強による植民地支配の実態も見聞しました。本国にあっては、近接準拠な民である欧州人がその東南アジアに向かえばなお暴虐の挙動を見る、という感想を残しています。一行は東南アジアで植民地支配の悲惨さを痛感すると同時に、弱肉強食の現実を受け止めました。「国として独立する大切さ、弱者側には回らない」という強い姿勢です。同様に岩倉使節団文書には「千古一日、開化の歩みをすすむことなく、いにしえのごとく野蛮な民はだなり」と記されています。もともと怠惰な国民性ゆえに進歩がないのだと痛烈な意見です。
明治時代とイギリスの影
こうして幕を開けた明治時代は、イギリスの脅威とどう向き合ったのでしょうか?イギリスは早くからグローバルな視点を持つ伊藤博文に目を付けていました。ジャーディン・マセソン商会を通じてロンドン大学に招き寄せ、うまく飼いならそうとしました。しかし、岩倉使節団による欧米視察が伊藤を変えました。アメリカはイギリスの脅威を伝え、ドイツのビスマルクはイギリスに対する大陸国家のあり方を伝えました。
実際、1872年に本格開業した日本初の鉄道建設の時、伊藤はイギリスから借款をすることを決めました。しかし、担保に日本の関税を要求されるとそれを拒否。交渉の結果、担保は関税収入のみに抑えられました。また同年、伊藤がいた大蔵省が作った国立銀行条例により、紙幣発行権が各銀行に与えられました。中国は紙幣発行権をイギリスに奪われ衰退しました。その失敗からの学びです。
30年後の1902年に結ばれた日英同盟はどうでしょうか?元老となった伊藤は満州高原鉄道を主張しました。日英同盟には反対し、単独でロシアへ交渉に向かいます。しかし、ロシアとの交渉はうまくいかず、日英同盟締結となりますが、この牽制が効いたため日本が主導権を握る形で締結となりました。
激動の幕末期:日本の巧みな立ち回り
日英同盟締結以降は第一次世界大戦を機に、金融の中心がイギリスのシティからアメリカのウォール街へ移ります。激動の幕末期、日本はロスチャイルド家が作り上げたイギリスという賢い敵を相手にうまく立ち回ったと言えるでしょう。選択を少し間違えれば、確実に今の日本はありません。今回は、幕末の歴史を振り返ってみました。また要望があれば続きを出そうと思います。お疲れさまでした。
